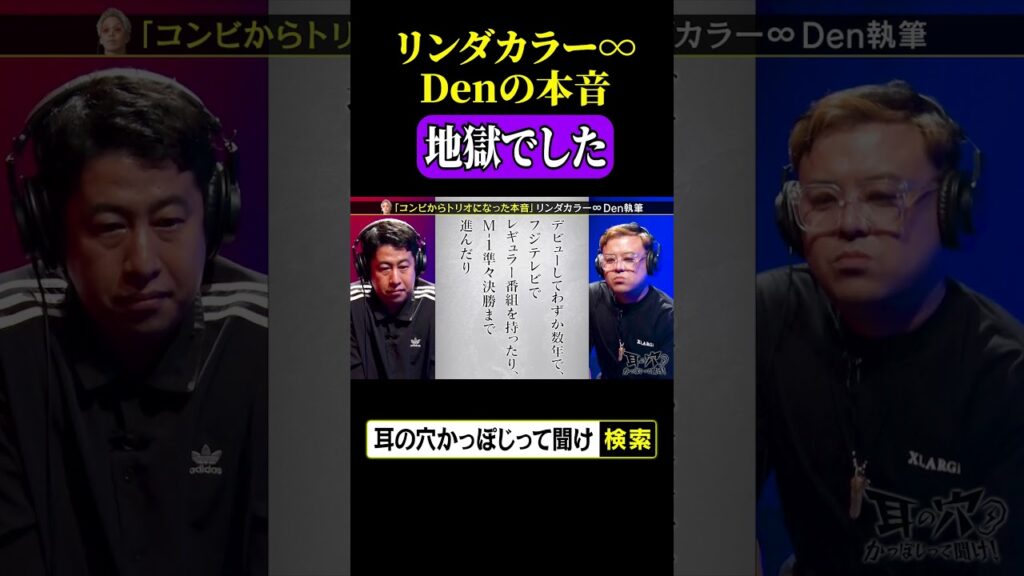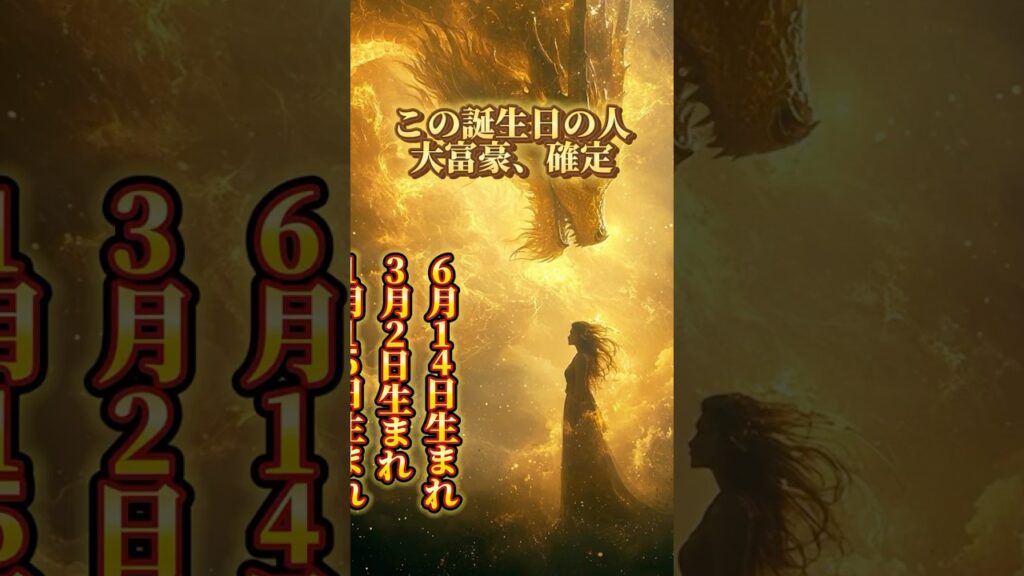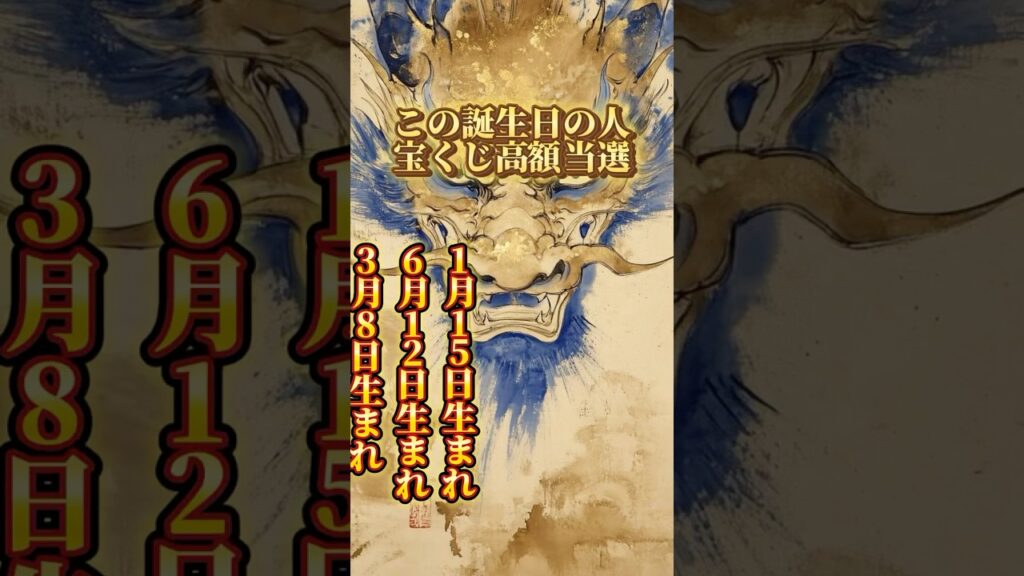【五代目 春風亭 柳昇(しゅんぷうてい りゅうしょう)】1920年〈大正9年〉10月18日 – 2003年〈平成15年〉6月16日)は、東京府北多摩郡武蔵野村(現:東京都武蔵野市)出身の落語家。本名:秋本(あきもと) 安雄(やすお)。ペンネーム:林 鳴平。出囃子は『お前とならば』。数々の新作落語を創作した。
来歴・人物
太平洋戦争中は陸軍に召集され、歩兵として中国大陸に渡ったが、敵機の機銃掃射で手の指を数本失っている。利き手をやられたため、元の職場に復職することもできず途方に暮れていたところ、戦友に6代目春風亭柳橋の息子がおり、その縁で生活のために柳橋に入門して落語界入りした。初高座は1946年12月1日の鈴本演芸場昼の部だった。
手を使った表現が多い古典落語では成功はおぼつかないと考え、新作落語一本に絞って活動して成功を収めた。ただ、数は少ないが古典落語のネタも持っており、『雑俳』や『お茶漬け(茶漬間男)』などを演じている。
年齢を重ねるごとに老人然とした風貌になり、しなびた声・口調に変わっていったが、これがとぼけた味となり、新作派の大御所として地位を確固たるものとしていく。80歳を過ぎても高座やテレビへの出演を積極的に続け、生涯現役の噺家であったが、表舞台での挙措に衰えが囁かれるようになった矢先の2003年6月16日、胃癌のため82歳で死去した。
日本会議代表委員を務めるなど、保守系の言論活動も行った。
次男はアニメ監督・アニメーターの知吹愛弓。
エピソード
落語家として
「春風亭」は元々初代麗々亭柳橋に遡る柳派の亭号である(春風亭柳枝など)。すなわち柳昇やその一門も柳派の系譜の一員である。
まだ二つ目だった時、横浜市の真金町の遊廓の慰労会に招かれて一席を披露したことがある。その慰労会での柳昇の落語を生で聴き、「自分も落語家になろう」と思った中学生がいた。その人物は椎名巖といい、後の桂歌丸その人である。
温厚で飄々とした芸風のイメージの持ち主であるが、1984年に所属する芸協が鈴本演芸場と絶縁した際、これを不服とした桂文朝、桂文生、桂南喬が落語協会に移籍したことを聞くと「あいつらとは二度と共演したくない」と激怒するなど、裏切りを許さず生真面目で頑固な一面も持ち合わせていた。
6代目三遊亭圓生が中心人物となり1978年に引き起こされた落語協会分裂騒動の際、圓生の直弟子の中から三遊亭好生と三遊亭さん生が師匠に逆らって落語協会への残留を選んだことから、圓生が両者を破門した上に芸名を剥奪するという事件が起きた。当時芸協の副会長であった柳昇は、好生について客分格の弟子として引き受けた当時の落語協会顧問8代目林家正蔵から相談を受ける形で、好生に「春風亭」の亭号の使用許可を与えており、事実上の“高座の孤児”となった落語家の救済という、当時大揺れの落語業界の懸案事項の解決に団体の枠を超えて一役買う格好になった。
『寄席は毎日休みなし』(うなぎ書房)と題する著書を著したが、寄席を休演することはあった。
メディア出演と「柳昇ギャルズ」
フジテレビで1959年に放送開始された番組『お笑いタッグマッチ』の司会役で人気が沸騰し、一躍時代の寵児となる。同番組のレギュラー陣には、同時に真打に昇進した10代目桂文治、4代目三遊亭小圓馬、4代目春風亭柳好、三笑亭夢楽がいた(他の出演者は落語協会の4代目柳家小せんと初代金原亭馬の助)。
自著『与太郎戦記』は、自身の軍隊体験を落語調に綴ったものでベストセラーとなった。大映で数度に渡り映画化されているが、その映画には自身もカメオ出演している。
1982年には落語好きの女子大生を中心に人気が集まり、彼女たちを中心に親衛隊ともいえる「柳昇ギャルズ」[注釈 1]が結成された。書記長は素人時代の木村万里(現・演芸プロデューサー)。さん生改め川柳川柳の弟子となる川柳つくしも一員だった。
松村邦洋はテレビ番組のロケで共演した際に「春風亭でぶ昇」の名を拝命されている。
漫画への登場
ゆうきまさみの漫画『究極超人あ〜る』に登場する春風高校の校長「柳昇(やなぎ のぼる)」の外見及び喋り方のモデルである。同作のイメージアルバムやサウンドトラックでは、特別出演としてこの役で声優も務めた。
柳昇校長というキャラクターのきっかけは、柳昇の次男でアニメーターの知吹愛弓とゆうきまさみの間に親交があったことである。知吹を介して柳昇本人から肖像権利用の許可を得て実現しており、本人公認のものである。なお、知吹は『あ〜る』では他にもイメージアルバムで曲垣役を演じ、1991年にOVAとしてアニメ化された際には監督を務め、知吹が経営する「スタジオこあ」がアニメーションの実制作を担当しているなど、同作とは縁の深い人物である。
次男の知吹愛弓とは、ツーショットでNTTの広告に出演したことがある(知吹については本名表記)。
私生活
1970年代、自宅から富士講に関する古文書など多数の資料が発見されるという出来事があった。これは先祖が、江戸時代に居住していた関前村(現在の武蔵野市)の富士講の指導者であったためである。
吉祥寺界隈など地元武蔵野市周辺での各種公演への出演後には、西荻窪駅南口にある鮨屋「松寿し」に好んで通っていた。
趣味の一つに将棋があり、1976年の新春にNHK教育テレビジョンで放送された『新春お好み将棋道場』では米長邦雄八段と四枚落ちで指し、解説の芹沢博文八段からヒントを貰いつつではあったが見事に勝利している(段位はいずれも当時)。
決まり文句
冒頭で必ず言うセリフが、「わたくしは、春風亭柳昇と申しまして、大きなことを言うようですが、今や春風亭柳昇と言えば、我が国では…(沈黙)、わたし一人でございます…」。「我が国では」の後の沈黙で観客が笑い出すことが多かった。
晩年は「もうこんなことを言うのも飽きちゃいまして…」と付け加えることもあった。
得意ネタ
結婚式風景
結婚披露宴で、めちゃくちゃな挨拶ばかりする来賓や仲人のスケッチ。
カラオケ病院
経営状態の悪くなったダメ病院が起死回生の策として、患者向けに「カラオケ」サービスを始める。『星影のワルツ』『お久しぶりね』などのヒット曲の替え歌を後半で披露。近年では弟子の2代目昔昔亭桃太郎も演じている。
課長の犬
「子どもが生まれた」という課長に挨拶に行くため、同僚におべっかの使い方を学んだ男。しかしその子供は「飼い犬の子ども(=子犬)」だった。
里帰り
嫁いだ娘が義母にいじめられていると聞き、「1年間は考えろ」と忠告しながら毒薬を渡す父親。1年後、振り袖姿で実家に現れた娘。義母との関係も良好。使わずじまいだった「毒」の中身は…。
南極探検
南極探検隊にいた、とウソばかりつく男の話。古典落語『弥次郎』の改作。7代目立川談志は柳昇から『南極探検』を教わり、『弥次郎』の息子が『南極探検』の主人公という設定にして、『弥次郎』と『南極探検』をつなげて『嘘つき二代』という題で口演した録音が残っている。
日照権
近所に高層マンションができるという情報が入り、町内会で「日照権はどうなる」と団体交渉の検討が始める。交渉係が大家のところに向かうが、ろくな結果にならない。
乙女饅頭
江戸時代の吉原を舞台にした新作落語。廓からの脱出を望む花魁が、金物問屋の奉公人と恋に落ちる。柳昇のヒューマニズムと日本古来の稲荷信仰が融合した人情噺。
与太郎戦記
自身の大東亜戦争体験を面白おかしく落語にしたもの。書籍版もあり、映画化もされている。ユーモアいっぱいの笑いの中に、さりげなく、敵機の機銃掃射によって凄惨な死を遂げる戦友や部下の話が語られる。
扇風機
免許証
小切手
税関風景
すきやき兄妹
雑俳
牛ほめ
三国志
お茶漬け
ほか
(ウィキペディアより)
【あらすじ】
隠居と八五郎の他愛ないやり取りから始まり、隠居の趣味である俳句の作り方を八五郎に教えてみるが、八五郎は頓珍漢な言葉をならべているだけでなかなか句にならない。